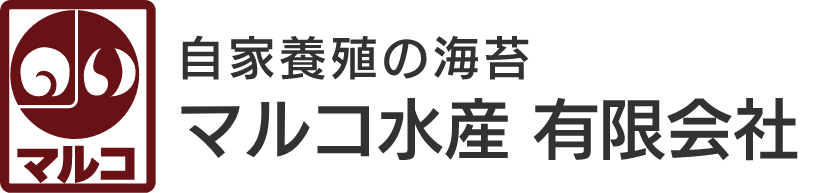マルコ水産について
ご挨拶

マルコ水産 二代目海苔師 兼田敏信(かねだとしのぶ)です。
平成2年に先代から引き継ぎ、マルコ水産有限会社を設立し代表となりました。
マルコ水産では、海苔養殖を核に、牡蠣養殖、春の定置網など、
年間を通じて田島の海で漁業をしています。
田島の「おいしい」を皆様にお届けし、
笑顔になっていただきたいという想いで日々取組んでいます。


マルコ水産の沿革
-
1964年
沼隈郡内海町(現福山市内海町)で初代兼田四郎が海苔養殖を創業
-
1990年1月11日
二代目兼田敏信がマルコ水産有限会社を設立
自家養殖の海苔を使った味付け海苔の外注加工、販売を始める -
2014年10月
自家養殖初摘みの生のりを使った「海苔師の生のり佃煮〈極〉」を開発、販売を始める
-
2015年4月
「生のりの佃煮」のバリエーションを追加
-
2016年5月10日
「海苔師の生のり佃煮〈極〉」が、第二回福山ブランドに認定
-
2016年12月23日
工場直販店「マルコショップ」をオープン
-
2017年6月30日
味付け海苔・焼きのりの加工ラインを導入、外注していた味付け海苔焼きのり加工部門を内製化
-
2018年5月
牡蠣養殖(オーストラリア式バスケット養殖)を始める
-
2020年1月31日
魚類忌避具(ギョニゲール)の開発
「魚類忌避具及び海藻養殖方法」PCT国際特許出願(出願国/日本・中国・韓国) 中国特許査定(2023年4月25日) -
2022年3月9日
「ギョニゲール」商標登録
-
2023年1月17日
「惑香-まどか-」商標登録
会社概要
| 名称 | マルコ水産有限会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒722-2631 広島県福山市内海町イ1427-28 |
| 設立 | 平成2年1月11日 |
| 資本金 | 300万円 |
| 取締役 | 兼田 敏信 |
| 事業内容 | 1.海苔の養殖、製造、加工、販売 2.定置網漁業 3.魚類に関する食害対策機器の製造及び販売業 4.牡蠣の養殖、販売 |
| 取引銀行 | 広島県信用漁業協同組合、中国銀行 |
マルコ水産の漁師たち
-
兼田敏信/2代目海苔師/社長

凝り性で何でもとことん突き詰めないと気が済まない職人気質。海苔師になる前は機械関係の仕事をしており、海苔工場の機械や船の修理なども全部自分でやってしまいます。ギターとゴルフが趣味。
-
兼田寿敏/3代目海苔師(兄)

長男。18年間小売業で腕時計の仕入れや販売促進に携わった後、2018年から家業に戻りマルコ水産へ。漁師として海の仕事もしつつ、営業部長として販路の拡大や、お客さんとのコミュニケーションにも力を入れています。単身赴任で休日には自宅と実家を往復する生活なので、趣味のゴルフにまったく行けないのが悩み。
-
兼田純次/3代目海苔師(弟)

次男。中学から大学までは野球一筋。海苔師になる前は10年間料亭などで料理人をしていました。その経験を活かし、今ではマルコ水産の看板商品になっている、「海苔師の生のり佃煮<極>」を開発。手抜きなし、妥協なし、空回りあり!そんな性格です。
-
おっちゃん

もう50年以上マルコに勤める超ベテラン漁師です。社長の従兄にあたります。海苔の収穫時期には、もぐり船(収穫船)の操縦を担当します。海苔時期以外は定置網や底引き網をしています。孫が7人いるおじいちゃん。孫が遊びに来ると、よく一緒に釣りをしています。
-
みっくん

漁師歴20年のベテランで、沖ではリーダーとして指揮を執ります。見た目はそんなにごつく見えませんが、ものすごい怪力。腕相撲は負けなしです。3代目のはとこにあたります。
-
かずま

おっちゃんの息子で3代目のはとこにあたります。田島漁協青年部会長も務めます。ミスチル大好き、特技はギター。海苔の製造中は24時間稼働する工場の夜勤を担当しています。海苔時期以外はおっちゃんと一緒に定置網や底引き漁に出ます。長身の大男だけど、お化けが怖いそうです。
-
なおき

2023年入社のマルコ水産最年少漁師ですが、入社時点ですでに漁師歴が5年以上の経験者!研究心が旺盛で、よく気が付くし、率先して動いてくれる、とても頼もしい存在です。よく真顔で冗談を言います。
-
村ぽん

牡蠣養殖を担当しています。鞆の浦でシーカヤックのお店の経営もしています。なんと元テレビマン!広島県のローカル番組では有名な「釣りごろつられごろ」のディレクターをしていました。時々お客さんと一緒にカヤックに乗って、海からマルコにやってきます。
漁業の未来について思うこと
漁業の未来を考えた時、よく言われるのが「後継者不足」「環境の変化」によって継続するのが難しくなっているということです。
確かに、後継者も減ってきているし環境も変わってきています。でも、その中でも必要十分な収入を得る方法はあると思うし、収入とやりがいが十分あれば、必然的に後継者は現れます。私達が考える漁業の最大の問題点は、ビジネスモデルの賞味期限切れです。


今の日本の漁業の基本ビジネスモデルは、漁師は獲ること(または育てること)に集中し、たくさん獲る努力をし、中間流通へ引渡し、市場や入札で買う側が価格を決定します。
でも、環境の変化など様々な要因で、昔に比べて漁獲は減っています。そんな中でも、たくさん獲ることを前提としている旧来のビジネスモデルでは生活できないので、後継者は現れません。全く獲れないわけではないし、獲れたものを喜んで食べてくださる「消費者」はいるわけです。ネット社会で世界中の方とつながることもできます。環境が変化しても育てる事ができる海産物も存在します。打つ手は無限にあるように思います。
田島がある福山市の場合、「芦田川」という大きな川が、河口堰で水がせき止められているため本来供給されるはずの川からの養分が遮断されて、環境が大きく悪化したという問題は確かにあります。それについて私達自身思うところもあるのですが、すぐにどうなるものでもない。今田島の若い漁師は、自分たちで販路を見つけたり作ったりする努力をして、一部は成果を上げつつあります。過去には、漁を見せた後、魚料理を振る舞う「定置網観光」をやっていました。今は諸事情で停止中ですが、獲るだけが漁師じゃないことを示した好事例だと思います。
そう考えると、付加価値の付け方も工夫次第です。
私達が考えるこれからの漁業のスタイルは、漁業者自身が、自らの生産品に付加価値を付け、価値に見合った価格を付け、お客様にその価値を伝える努力をし、喜んで買っていただけるというお客様とのよき関係を築き、その結果生活していくのに十分な収益を得る。こういうサイクルが理想的だし、やりがいもあるし、なによりお客様が喜んでくれている姿を間近に見られるので、やっていて楽しい。「お客様」が消費者であっても、業者さんであっても同じことです。相手が業者さんであれば、協力して価値を伝道して、消費者まで伝わるようにすればいい。
田島の若い漁師は、みんな今置かれた環境で、できることを真剣に考えています。私達は、少なくとも「田島」の漁業の未来は明るいと信じています。